 悩む人
悩む人「Google先生、近代や現代の世界が舞台の面白い歴史小説を読みたいです!」
…と聞いてみても、望む検索結果がなかなか出てこない。古代のローマ?三国志の中国?幕末の日本?いや、ちがう!
求めているのは近代・現代の世界が舞台のエンタテインメント風な小説よ。
…という方向けの記事です。
探している小説のイメージをもう少し具体化すると以下のとおり。
- 歴史上のできごとのなかで、
- 教科書に載るような人が活躍したり、
- スパイ・諜報員が暗躍したりして、
- 近現代ならではの歴史の「if」や「タラレバ」に想いを馳せ、
- なんともいえない読後感に浸りながら、気付けば教養が身に付いている(?)
え?
「注文が多すぎる。だったらオマエがリスト作れや」ですって?
ほっほーっ、望むところですよ笑
では、ぼくが独断と偏見でおすすめの名作をランキング化してご覧にいれましょう!
全部で30作品を取り上げます。
このランキングが、世界史x近現代の歴史小説にエンタテインメントを求めてやまない全ての人へ、役立ちますように。
世界史の受験や勉強に追われている若者への癒しになりますように^^
【歴史小説】世界史香る海外が舞台の小説おすすめ30選(近代・現代)
- 順位はぼくの独断と偏見です😌
- 舞台となった時代や地域、ぼくの紹介コメントを載せてます
- ランキングはTOP10までは1作家1作品でして、それ以降は順位なしの作家順です
- ランキング圏外でも、面白くて読みやすい作品の自信アリ!是非手に取ってみてください
- 冒頭にAmazonから商品紹介欄を引用していますので、概要把握にお役立てください
1位:黄砂の篭城(松岡圭祐)


テーマは義和団事件。
いきなり世界史臭がしますよね笑
世界史の教科書に、おそらく太字で書かれているこの事件について、ほとんどの人は聞いたことあるでしょう。
でもね、意外と具体的には何も知らない。
ましてや、この本の帯にあるような「実は柴五郎という日本人が活躍した」なんて話は知る由もないです。
でも、知らないからこそ面白いんですよ!
2位:ワイルド・ソウル(垣根涼介)


ブラジルといえば、「日系移民が多い」を想像すると思うのですが、さて問題です。
なぜ、ブラジルには日系移民が多いのでしょう?
なぜ、わざわざ日本から地球の裏側に移民しちゃったんでしょう?
…ってことを、どうして誰も教えてくれないんだろうね。
知っちゃいけないことを知ってしまったような背徳感と圧倒的スピード感に「これぞ俺の求めていたエンタテインメント!」と雄叫びをあげながら一気に読めちゃいますよ!
3位:蒼穹の昴(浅田次郎)
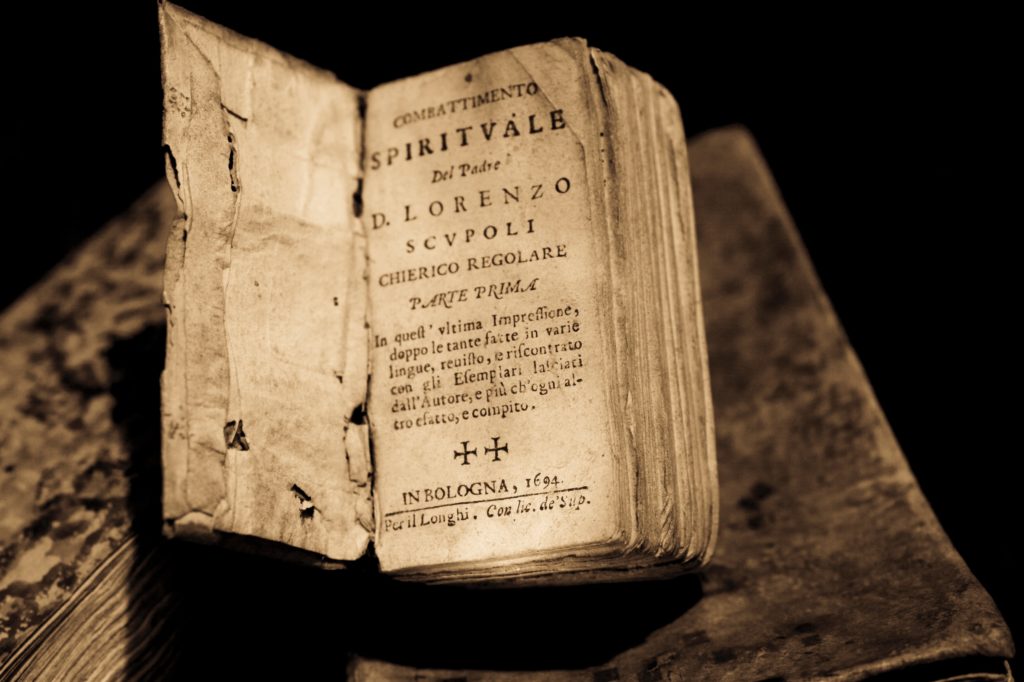
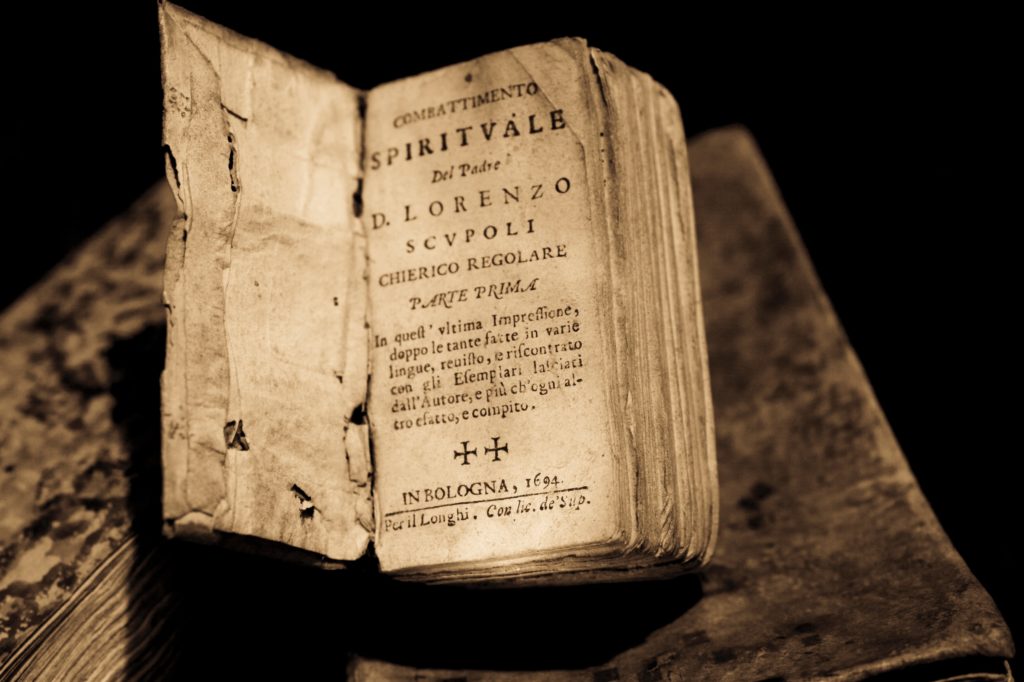
1位でご紹介した義和団事件が起きたまさにその前後に、中国の新王朝では何が起きていたか。
それが非常によく分かる作品です。
内容が素晴らしいことに加えて、日本が「宦官」制度を中国から輸入しなくて本当に、本当に、本当によかった……!と思うくらい、宦官についての描写が細かすぎてビビります。
宦官(かんがん)とは、去勢を施された官吏である。去勢技術は家畜に施すものとして生まれたため、宦官は牧畜文化を持つ国にのみ存在するという説があるが、現実には牧畜文化を持たない国においても宦官は存在した。
宦官 – Wikipedia
登場人物には、伊藤博文や西太后はもちろん袁世凱や李鴻章、柴五郎まで出てくる感じで清王朝末期のオールスター感があります。
4位:プラハの春(春江一也)


小さいころ、我が家には地球儀がありまして。
そこには「ソヴィエト連邦」が載っていて、お父さんに「もうすぐここ(ソヴィエト連邦)がなくなるんだ」なーんてことを教えてもらったような。
今でこそ、西側とか東側とか、資本主義とか共産主義とかって全く聞かなくなったけど、当時は大変な時代ですよね。。
そして、そんな時代の外交官はやりがいがあったことでしょう。
本当にこんなことが半世紀前にあったのかと思うくらい、心の臓に響く作品です。
5位:龍の契り(服部真澄)


テーマはずばり香港返還。
ちょいときになるのが、この本、ひょっとして絶版か何かになったのか?
正規の本の流通量が少ない気がします。
ひょっとしたら、香港返還に関して何らかまずい話が載っていたのかも?!
でも、確かに不思議でして、どうしてイギリスは香港を返還しちゃったんでしょう。
事実は知らないけど、「事実は小説よりも奇なり」だと思わされる1冊です。
6位:不毛地帯(山崎豊子)


「シベリア抑留」って言葉では聞いたことはあった。
ただ、抑留って言っても、シベリアに連れて行かれて〜くらいのことしか知らなかった。
正直、この本を読むまで「シベリア抑留」の実態をナメてました。
まさに地獄。
信じられないほどの厳しさ・理不尽さ・無慈悲さで、思わずどん引きします。
ドラマになるくらいだから内容は間違いないですよ!
登場する会社は「伊藤忠商事」がモデルと言われていますね。
7位:海賊と呼ばれた男(百田尚樹)


比較的最近の本です。
有名なのでご存知の方もいるのでは?
「日本とイランは仲が良いのはなぜだろう?」という人に読んでみてほしい作品です。
また読みたくなる良い名作でして、「出光興産」がモデルと言われていますね。
8位:スギハラ・サバイバル(手嶋龍一)


「第二次世界大戦中、ユダヤ人を沢山救った日本人がいた」。
そんな話を聞いたことがあるとしたら、それは杉原千畝さんのことですよ。
どうやって、どんな理由で第二次世界大戦下、ナチスドイツと同盟中の日本がユダヤ人を救ったのか。
そして、ユダヤ人は日本へのビザを発給してもらったとしても、当時どうやって国を脱出し日本まで来たのか。
母国から着の身着のまま、家族とともに駆け抜けたであろう道中に、想像を絶するほどの不幸や苦難がないわけがない。
その具体的な事象も詳細に描かれていて、胸が詰まります。
9位:流(東山彰良)


台湾は出張で1回行ったことがあって、本当に親日で良い国ですよね。
ただ、台湾の歴史については「蒋介石」「国民党」くらいしか知りません……って人にピッタリな小説です。
日本語の表現が秀逸で、何度も同じ文章を読んじゃうこと請け合いです😌
「1968年台湾生まれ。5歳まで台北で過ごした後、9歳の時に日本に渡る。」という著者だからこそ、描けるリアルな描写がすごいですよ。
10位:タックスヘイブン(橘玲)


マネーロンダリング(資金洗浄)について書かれた小説ですが、単なる金融系の本ではありません。
舞台のシンガポールがどんな国か。
どんなことを意識することを宿命づけられた国か。
読みながらそんなことを学べます。
ノミネート:また、桜の国で(須賀しのぶ)


昔のぼくは、ポーランドと聞いて「アウシュヴィッツ」しか思い浮かばない人でした。
でも、この本を読んだ今は違います。
ポーランドの意味=「草原の国」を謳うほど、広大な平野を持つ豊かな国。
草原の国ゆえに自然の防波堤がなかったことで、何度も欧州列強の侵攻に合い、世界地図から消えては蘇ってきた不屈の根性のある国。
そして、有名な音楽家ショパンを輩出した国。
この小説を読んで以来、ショパンの『革命のエチュード』を聴きまくっています。
ノミネート:革命前夜(須賀しのぶ)


舞台は冷戦下のドイツです。
国家保安省(シュタージ)の監視の目がある東ドイツへ、純粋な気持ちで音楽留学した若者の数奇な運命を描きます。
歴史&音楽&青春の3重奏な小説ですが、いかんせん「音楽」の話なので、ピアノやヴァイオリンの話がたくさん出てきます。
「音楽はよく分からないぞ?」という人も大丈夫。
だって、ちんぷんかんぷんのぼくでも楽しめましたから。
後半になるにつれ、帯に書かれている「ーこの国の人間関係は2つしかない。密告するかしないかー」の意味がよく分かります。
ノミネート:リボルバー・リリー(長浦京)


近現代の日本の歴史小説って、日清日露戦争と第二次世界大戦を題材にしたものが多い気がしませんか?
でも、実は、その間にも関東大震災や治安維持法などがあったわけで。
そのときの時代描写を小説で学びたい人にはこちらです。
本のタイトルからして、スパイや諜報員の匂いがプンプンしますよね。
ノミネート:海の翼(秋月達郎)


「日本とトルコって仲良いんでしょ?」
その話を聞いたことはあっても、「でも、どうして日本とトルコは仲がいいんだっけ?」と聞かれたら「はにゃ?」となる人もいるはず。
歴史的には明確に背景がありまして、「エルトゥールル号遭難事件」がそれですね。
フセイン大統領からムスタファ・ケマル、真田真之に福沢諭吉まで登場するので、近現代好きにはたまりません。
話の結論が分かっていても、涙が溢れる内容です。
ノミネート:総督と呼ばれた男(佐々木譲)


『海賊と呼ばれた男』は知っていても、『総督と呼ばれた男』は知らないでしょう?
舞台はシンガポールとマレーシア。
「大正時代から昭和時代初期の戦争に突入する前に、もし、シンガポールにいたとしたら……?」
当時イギリス領のシンガポールに、戦争と日本軍の足音が聞こえてくるリアルさがたまりません。
ノミネート:ベルリンの秋(春江一也)


当記事で取り上げた「プラハの春」の続編です。
読み終えた深夜に、1人涙を流した記憶があります……
多少の誇張はあったとしても、こんな世界がたった四半世紀前にあったなんて信じられないですよね。
ノミネート:ウィーンの冬(春江一也)


「プラハの春」「ベルリンの秋」のさらなる続編で、シリーズ的に読み進めることが出来ますよ。
次の舞台はオーストリア。
何よりも、ウィーンを舞台にした小説ってあまりありません。
ぼくはたまたま卒業旅行で1回行ったことがあるんですが、「そういう国だったんだ…」という発見が多かった。
ノミネート:上海クライシス(春江一也)


「新疆ウイグル自治区」と聞くと、血なまぐさい事件を思い浮かべる人もいるでしょう。
実際に現地で何が起きてるのかは詳しく知らない方は、小説で(不謹慎ですが)疑似体験として、エンタテインメントとして本書を読むのは有益だと思います。
まずは断片的でもいい、世界で何が起きているかを知りましょう。
話はそれからです。
ノミネート:D機関情報(西村京太郎)


「永世中立国」スイスに関する小説はあるのかしら、と調べて見つけたのが本作です。
第二次世界大戦当時に中立国に渡ることがどれほど大変だったか。
中立国であるがゆえに各国の情報機関が暗躍し、誰が味方で誰が敵か。
スパイってかっこいい印象もありますけど、決して当事者にはなりたくないなと思わされました。
ノミネート:69(村上龍)


1969年にルーツのある、遊んだようなタイトルを付けて読者を驚かせて、ほくそ笑む村上龍(笑)
…を尻目に、世界的な学生運動絶頂期に日本の若者はどうだったかを知れる良書です。
楽しく読めますよ。
ノミネート:1984年(ジョージ・オーウェル)


今でも思い出します。
この小説のクライマックスなのかな、読んでいて急に頭が「えっ?」てなる部分。
そのときの、頭に鳥肌が立つというのか、脳みそをえぐられるような……。
そんな衝撃だけは未だに残ってます。
最近だと、来る政府による監視社会(?)を予言した小説として紹介されることも多いですよね。
ノミネート:ダ・ヴィンチ・コード(ダン・ブラウン)


ぼくは大学生のときに卒業旅行でイタリアに行きました。
その時はまだこの本は発売されていなかったんですよ。
当時は美術に興味なかったですし、お金もなかったので、入館すらしなかったフィレンツェのウフィツィ美術館。
この小説を読んでいたら、きっと楽しめたんだろうなと思います。
行きたかったなぁ……
ノミネート:大地の子(山崎豊子)


当記事で紹介した、台湾が舞台の作品『流』と同時代の1970年ごろの中国はこんな感じだった、という比較で読むと面白いです。
全4巻、読み終わった後のなんともいえない読後感が今でも思い出されますね。
実際に今、改めてこの紹介文を読んでも胸がギューっ、てなるもんなぁ。
ノミネート:二つの祖国(山崎豊子)


これまた胸がキューっと締め付けられる、だけど、どんどん読みたくなる小説です。
「戦争って究極のコンテンツの1つだよね。」
確か、そんなことをネット界の有名なブロガーのちきりんさんが言ってたんだけど、まさにそう。
「事実は小説よりも奇なり」のエピソードがコレでもかコレでもか、って生み出されてます。
ノミネート:生きている理由(松岡圭祐)


この本を読むまで、ぼくは知らなかったのが主人公の「川島芳子」。
東洋のジャンヌ・ダルクだそうですよ。
とにもかくにも『生きている理由』というタイトルをぶつけてくるあたり、読めばなるほどって膝を打つはず!
そして、この本は続編を読みたくなる。
「激動の青春篇」との触れ込みだから次があると思ったら、無さそう……それは悲しい。。
ノミネート:ヒトラーの試写室(松岡圭祐)


まさかウルトラマンで有名な円谷英二の人生に、ナチスやヒトラーが影を落としていたなんて。
ナチスが国内世論を巧妙に誘導するために、プロパガンダを行ったことをご存知の方は多いでしょう。
そのために扱ったタイタニック沈没や戦争などの悲劇を、臨場感持って伝えるために磨かれたのが、特殊撮影技術であり。
それが花開いたのが、ウルトラマンという舞台です。
こんなことをウルトラマンファンが聞いたらどんな反応をするんだろう?
それにしても、この時代の人たちはみんな本当に命削って仕事してますよね。
ノミネート:八月十五日に吹く風(松岡圭祐)


題名からは「なんとなぁ〜くこんな話なんだろ?」と想像つきそうですよね?
だけど、おそらくそれは裏切られる形でストーリーは続きます。
時は第二次世界大戦、舞台は日付変更線よりも先にある島、「キスカ島」です。
テーマはキスカ島撤退作戦であり、のちに「奇跡の作戦」と呼ばれるもの。
Wikipediaに載るくらいの一大作戦でして、非常に面白いです。
『八月十五日〜』というタイトルは重たいけれど、命の尊さを感じられる小説です。
一度読んだら最後、毎年8月15日くらいにこの小説の存在を思い出しちゃいますよ。
しかし、戦時中の日本は信じられないくらい遠いところまで戦地として繰り出していたんですね。
日付変更線て……
ノミネート:シャーロック・ホームズ対伊藤博文(松岡圭祐)


ぼくはシャーロックホームズの本はほとんど読んだことがないですが、タイトルからして興味を掻き立てられます。
舞台は大津事件。
ご安心ください。
シャーロックホームズも、大津事件も、どちらも知らないぼくも楽しく読めましたから!
アメリカでも英訳出版され重版されるほど、海外からの評価も高い作品。
NYヴァーティカル社編集者ヤニ・メンザスは「(著者の松岡圭祐氏を)世界に誇るべき才能」と評したと話題になりました。
ノミネート:グアムの探偵(松岡圭祐)


リゾート地としてハワイと並び立つ雄、グアム。
実は僕はいったことないのですが、華やかなイメージがあります。
ところが、実はそれはグアムのほんの一面しか捉えていないことに気付かされます。
ちなみに・・・僕はこれを読んで家族とグアムには行きたくないと思いました笑
だって、想像以上に怖そうなんだもん笑
小説は大人気でして、あっという間にシリーズ化、3冊発売されてますよ!
ノミネート:落日燃ゆ(城山三郎)


総理大臣の名前を覚えたことがある人なら「広田弘毅」の名前を聞いたことはあるでしょう。
A級戦犯のなかで、ただ1人の文官。
以前に読んだけど、悲しい記憶しかありません。
ノミネート:異邦の子(西川司)


よくニュースで見聞きする「イラク」という国。
でも、ニュースからでは、その地が最高50度を超える灼熱の大地だということは伝わってきません。
でも、この本は違う。
「ひょんなことから日雇いのアルバイトでイラクに行き、そこでイラン・イラク戦争に巻き込まれた」という数奇な経験をした筆者渾身の小説だからこそ伝えられる、リアリティがそこにはあります。
番外編:アドルフに告ぐ(手塚治虫)


番外編として、小説ではないマンガのご紹介。
著者はかの有名な手塚治虫。
題名からお察しの通り、ナチス時代のドイツを起点にしながらも、日本・イスラエル・パレスチナとスケール大きくストーリー展開する手腕はまさに一読の価値ありでして、もはや漫画じゃない……
『漫画芸術の最高傑作』とも称される、超一級品です。
【歴史小説】世界史香る海外が舞台の小説おすすめ30選(近代・現代)|まとめ
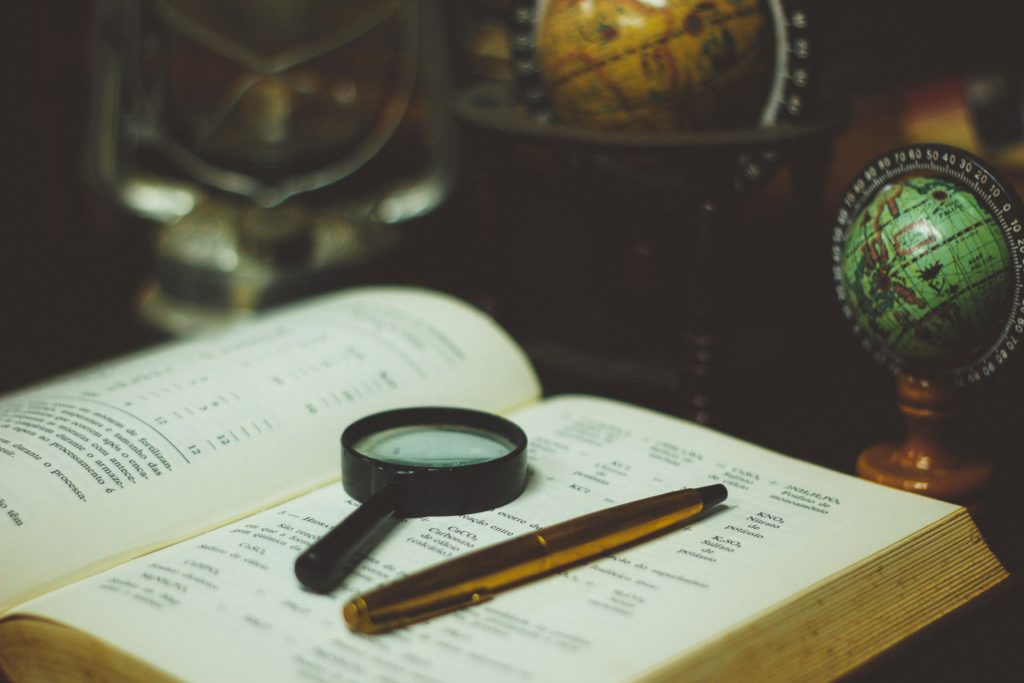
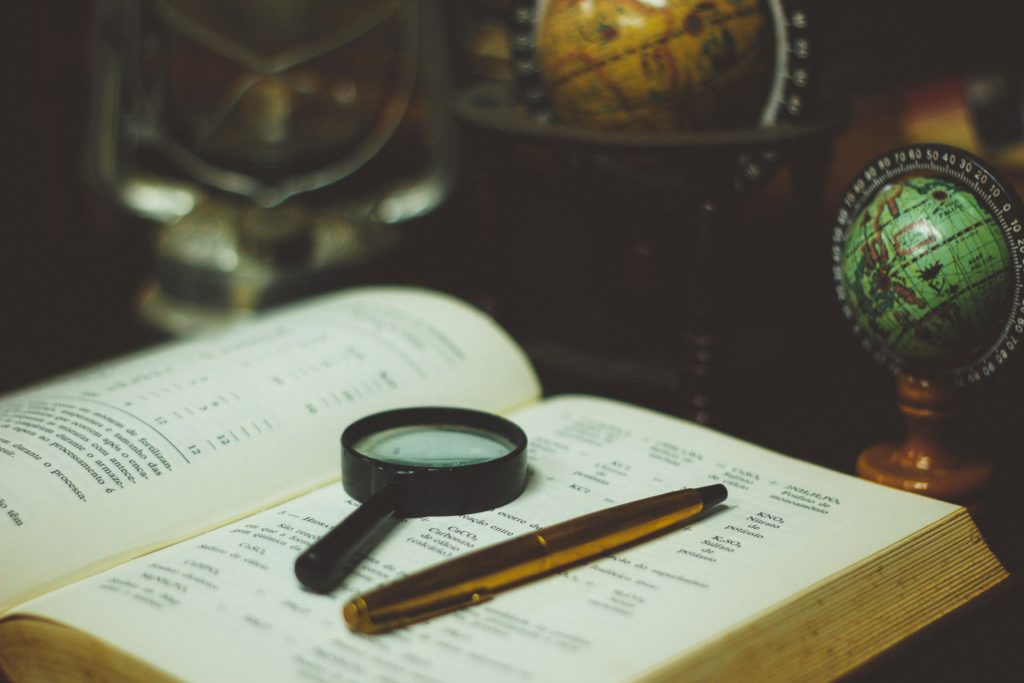
というわけで、ランキング付け・・・力尽きました笑
改めて取り上げた全30作品の一覧は以下のとおりです。
- 1位:黄砂の篭城(松岡圭祐)
- 2位:ワイルド・ソウル(垣根涼介)
- 3位:蒼穹の昴(浅田次郎)
- 4位:プラハの春(春江一也)
- 5位:龍の契り(服部真澄)
- 6位:不毛地帯(山崎豊子)
- 7位:海賊と呼ばれた男(百田尚樹)
- 8位:スギハラ・サバイバル(手嶋龍一)
- 9位:流(東山彰良)
- 10位:タックスヘイブン(橘玲)
- ノミネート:また、桜の国で(須賀しのぶ)
- ノミネート:革命前夜(須賀しのぶ)
- ノミネート:リボルバー・リリー(長浦京)
- ノミネート:ベルリンの秋(春江一也)
- ノミネート:ウィーンの冬(春江一也)
- ノミネート:上海クライシス(春江一也)
- ノミネート:総督と呼ばれた男(佐々木譲)
- ノミネート:D機関情報(西村京太郎)
- ノミネート:69(村上龍)
- ノミネート:1984年(ジョージ・オーウェル)
- ノミネート:ダ・ヴィンチ・コード(ダン・ブラウン)
- ノミネート:大地の子(山崎豊子)
- ノミネート:二つの祖国(山崎豊子)
- ノミネート:生きている理由(松岡圭祐)
- ノミネート:ヒトラーの試写室(松岡圭祐)
- ノミネート:八月十五日に吹く風(松岡圭祐)
- ノミネート:シャーロック・ホームズ対伊藤博文(松岡圭祐)
- ノミネート:グアムの探偵(松岡圭祐)
- ノミネート:落日燃ゆ(城山三郎)
- ノミネート:異邦の子(西川司)
- 番外編:アドルフに告ぐ(手塚治虫)
上記で満足できないという人は、NHKの映像コンテンツ『映像の世紀』を観ることをオススメします。
妻に『映像の世紀』を見せたところ、「この番組ってすごい…」と衝撃を受けていました笑
今回は以上です。
ほんだらのー!
本記事で多々登場する小説家、松岡圭祐さん。
歴史小説以外にも推理系・ハードボイルド系を手がけてらっしゃいます。
どれも一級品で、最近は『高校事変』が数ヶ月に1冊ペースで発売されていますよ💡

































