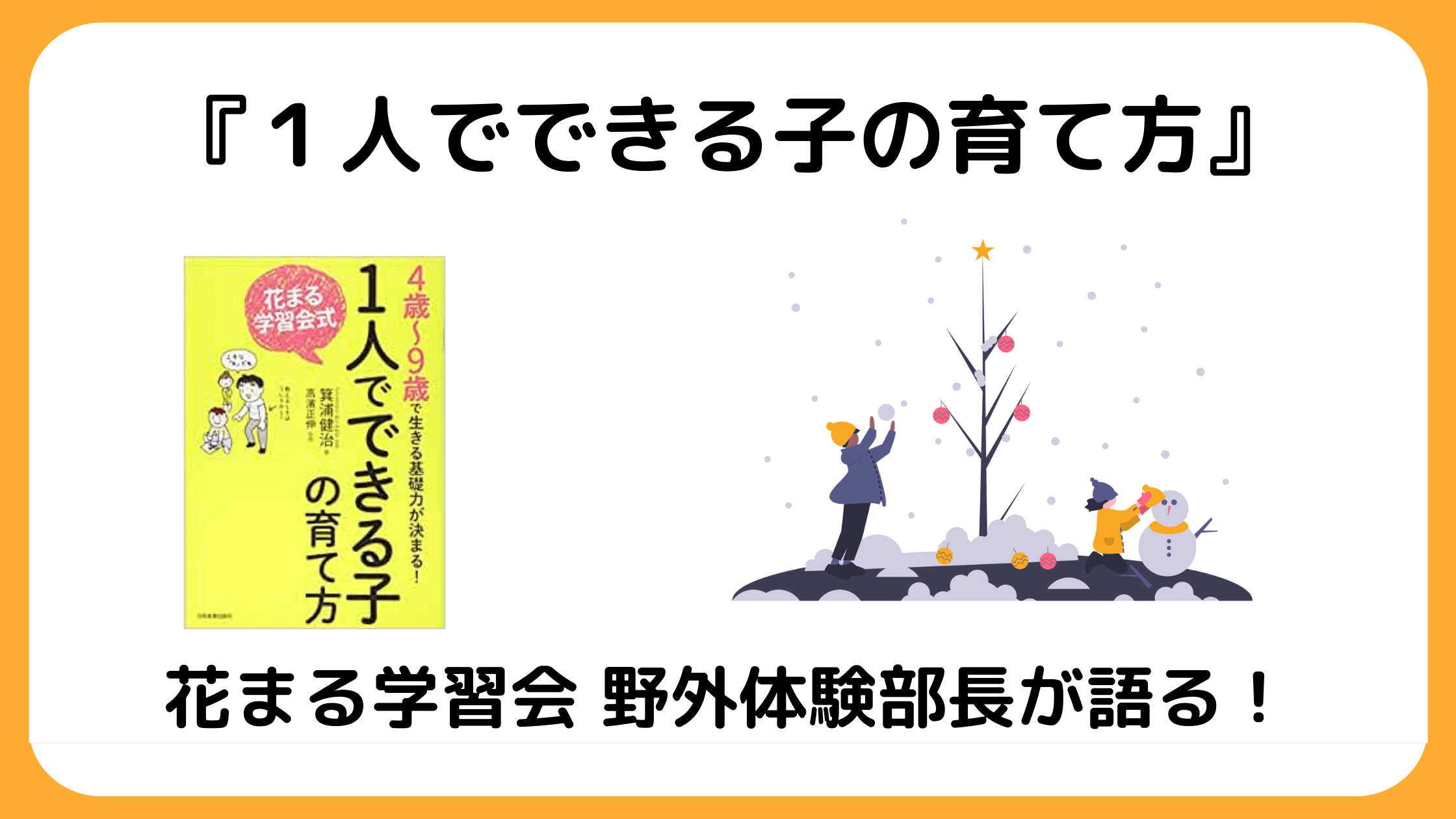悩む人
悩む人親向けに子育てのマインドを説く本はたくさんあるんだけど、別に、説教を読みたいわけではないんだよ。もっと、実用的な本はないもんかね?
そんなことを妄想してたときに出会ったのがこの本でして。
マインドではない、実際にこう接したほうがいいという行動ベースの事例が豊富で参考になりました。
早速読了したので、以下についてまとめます。
- どんな人が書いたか(著者)
- そもそもどんな本か(内容や要約)
- どんな人にオススメの本か
それでは行きましょう!
『1人でできる子の育て方』の基本情報


著者・出版社・出版日など
| タイトル | 花まる学習会式1人でできる子の育て方 |
| 副題 | 4歳~9歳で生きる基礎力が決まる! |
| 著者 | 箕浦 健治 (著), 高濱 正伸 (監修) |
| 出版社 | 日本実業出版社 |
| 出版日 | 2016/5/28 |
箕浦 健治さん(著)、高濱 正伸 さん(監修)のプロフィール
Amazonの著者紹介の欄をサマるとこうなります。
箕浦 健治さん(著)のプロフィール
- 野外体験アルバイトの豊富な実績を買われ、花まる学習会に入社
- 花まる学習会野外体験部部長として現在に至るまで、延べ5万人を引率
- 愛称は「ファイヤー」、花まる学習会の日本一と名高い野外体験教育の基盤を築く
高濱 正伸 さん(監修)のプロフィール
- 花まる学習会代表
- 学力や引きこもりの問題は、思考力と生きる力の不足が原因と確信
- 幼児教育に必要なのは、さまざまな体験の蓄積だと提唱
「花まる学習会」の野外体験部長(著)・社長(監修)の本
平たく言えば、こんな本です。
ちなみに、1人の親として言いますが「はなまる学習会」、めちゃ伸びていますね。
ちなみに、はなまる学習会の野外体験も有名です。
自然の中で過ごす体験だけでなく、「親との連絡一切禁止」、「友達同士の参加禁止」という新しい切り口で「ミニ社会」の経験を積ませることを重視していますよ。
『1人でできる子の育て方』の要約


では、ここからは、要約・感想です。



親向けに子育てのマインドを説く本はたくさんあるんだけど、別に、説教を読みたいわけではないんだよ。もっと、実用的な本はないもんかね?
↑こちらのとおり、特に実用的だと印象に残ったものを中心に、3点ご紹介します(一部、引用を含みます)。
子どもは集中力がありすぎて話が聞こえない前提で接する
いきなりですが、これとかハッとしませんか?
<何度言っても聞かないのは、本当に聞こえていないから>
「叱らないで、具体的な指示を出してあげてください」と私が言うと、「だって先生、何度言っても聞かないから怒っちゃうんですよ」とおっしゃるご両親も多いのですが、これもまた、幼児期の子どもにはよくあることです。
というのも、この時期の子どもはわざと聞かないのではなく、遊びやテレビに集中しすぎると親の言葉が聞こえなくなってしまうのです。
4〜9歳の幼児期の子どもは好きなことには驚くほど夢中になります。
その夢中になっているときに、たとえば「ご飯だよ」と言われても返事はできません。なぜなら聞こえていないからです。
親としては、絶対に聞こえているはずの大きな声で何度も言っているのに子どもが振り向きもしないことにだんだん腹が立ってきて、ついには「さっきからご飯だって言ってるじゃない!」と怒鳴ってしまいます。
ところが、子どもからしたら「突然、お母さんが怒った顔で自分を見ている」とびっくりなのです。お母さんにとっては「聞こえているはず」の声も、夢中になっている子どもには聞こえていないのです。
#本書より引用
じゃあ、どうすればいいのかという話ですが、それは本書をご覧くださいませ。
ちなみに、子どもは視野も狭いらしいです。
おもちゃを片付けするときに、目の前におもちゃが転がっているのに子どもはまったく気付かなくて、親はよくイライラするんだけど、彼らは実は見えていない、ということのようです。
彼らに悪気は全くないんだけど、親であるぼくはイライラw
教えるときは子どもの前ではなく後ろから
これまたハッとさせられる内容です。
<教えるときは子どもと同じ方向を向く>
「うちの子、どうも漢字が苦手で」という相談も、とても多いものです。
(中略)でもじつは、これも教え方の工夫で解決できます。それは、教えるときは「子どもと同じ方向を向いてやってみせる」ということ。
たとえばボタンの留め方を教えるとき、子どもの正面に立ってやってみせていませんか?
しかしそれでは手の動きが左右逆になるので、こどもにはわかりにくいのです。
そんなときは後ろに立って、子どもの手に自分の手を添えて教えれば、どのようにボタンやボタンホールを掴むのかが、子どもにもすんなり伝わります。
#本書より引用
ぼくの場合は、まさに「あちゃー」という感じ。
ぼくも子どもの方まで歩くのが面倒で、正反対に向きながら文字を教えてたりしてました汗
外で汚れて遊ぶ
もう思い当たる節しかありませんね。。
<汚れて遊ぶ楽しさを親子で体験する>
野外体験の行き先は雪原や渓流だったりするので、地面や草の上に直に座ることもしばしばです。
そんなときに、「汚い」「汚れる」と言って草の上に座れない子どもが最近すごく多いのです。
「布団を外に干して、ばい菌がつかないんですか」と聞いてきた子どももいました。
中には病的に潔癖性な子もいますが、単に、「自分の家以外の場所はきれいじゃない」と暗に教わっている子が多いように思います。
「汚いでしょ」とつり革を触らせない。草の上に座らせない。そういうことが繰り返されると、子どもは、草は汚い、電車は汚い、家以外は全部汚い、と覚えてしまうのです。
実際、野外体験に初参加する子のご両親からは「トイレは洋式ですか?」という質問も多いです。
和式が使えないというよりも、「和式は汚い」と思う心が働くようです。
#本書より引用
ぼくも、子供が歩きながら道端の壁や柱にタッチすると「汚いからやめて」と言いますし。
一方で、「和式トイレは汚い」にぼくも同意です汗
『1人でできる子の育て方』の要約|まとめ
あとあと何も残らない子育てマインドではなく、子供とどう接するかの具体的な事例が豊富な点がオススメの書籍です。
その他、QAもたくさんです。
Q:娘が父親を嫌っています
Q:妻が子どもをダラダラ長く叱ります
Q:休みの日に旦那がゴロゴロしています。子どもに悪影響はありませんか?
Q:ひとり親家庭です。「両親の役割分担」ができません
Q:子どもが「みんなもっている」とデーム機をねだります。本当は与えたくないのですが
著者と監修者所属の、学習塾「花まる学習会」での圧倒的な場数がなせる情報量ですね。
そんじょそこらの育児本とは違う切り口で面白いですよ。
『1人でできる子の育て方』はこんな人に読んでほしい


子育て中の親御さんなら等しく読んでおいていいかもです。
いつ誰が言ってたのか分かりませんが、子育てに正解はないという噂を聞いたことがあります。でも、この本を読むと「ひょっとしたら、こう接した方が子どもにとって望ましい的なものはありそう」なんて思ちゃいました。
合わせて、書籍「『忙しいビジネスマンのための3分間育児』の要約まとめ」もオススメですよ 😀
全力でオススメできる良書ですので、興味のある方はどうぞ。
ほんだらのー!